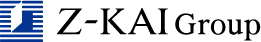執筆者
石山 純也
中野校校長 / 富士・大泉高校附属中学校専門担当
-
所属教室
お子さまがすでにE-styleに通われている保護者の皆様には、日々の授業や課題、面談などを通じて、「E-styleの特色」を感じていただけているものと存じます。
一方で、「他の塾と比べてどうなのか?」という視点が気になるということもあるかもしれません。今回は、「E-styleと他塾の違い」をテーマに、E-styleにご通塾いただいていることの強みを最大限に活かす方法を考えたいと思います。
まだご通塾でない方も、ぜひE-styleの特色を知っていただければ幸いです。
1.志望校に直結する学びで「全員合格」を目指す!
E-styleの大きな強みは、「志望校に特化したカリキュラム」です。ご存知の通り、E-styleでは、校舎ごとに「○○中対策コース」と銘打ったコースを設け、入試傾向を徹底的に分析した授業が行われています。また、「ボーダーライン」と呼ばれる適性検査当日の得点と学校の成績を換算した報告書点の合算得点の目安を、各校舎が志望校ごとに把握していることも他塾にはない強みと言えます。
一般的な大手塾では、「公立中高一貫校コース」「私立中受験コース」など幅広い志望校に対応するためにコースが設定されています。それに伴ってどうしても学習範囲が網羅的に広くなり、授業時間や課題量が膨大になる傾向があります。
そうして「第一志望に本当に必要な勉強」が埋もれてしまうことも少なくありません。
E-styleでは必要な部分を絞り込んで効率的に取り組むため、無駄が少なく「この勉強が合格につながっている」という実感が得やすいのではないでしょうか。
また、学習時間の縛りがきつくない分、低学年のうちは習い事との両立をしたり、基礎学力の充実を図ったり、絶対合格を目指してさらなる特訓をしたりすることができます。
さらに、こういった環境で「みんな同じ志望校」を目指すのもほかの塾との大きな違いです。クラスメイトはライバルであると同時に将来の同級生であり一生の友達です。受検が孤独な戦いにならないのは、小学生にとっては大きな励みではないでしょうか。
こういったメリットを最大限に活かすためにも、志望校はなるべく早めに絞り込んでいきたいものです。
2.少人数制・双方向授業で「知の共有」
次に注目したいのが、授業スタイルです。
E-styleは少人数制授業を基本とし、先生が一方的に解説するのではなく、生徒の発言や思考を引き出す「双方向型授業」を重視しています。「なぜそう考えたのか」「別の方法はないのか」といった問いかけを通じて、生徒は自分の言葉で説明する力を養います。
自分一人だけの勉強では限界があります。「なるほどそんな考え方もある」「へぇ、そうやって工夫するのか」と、お友だちの話を聞いて視野を広げられるのがE-styleのいいところです。
これに対して、大手塾ではクラスの人数が多くなる傾向があり、授業は効率重視の講義型になりやすい面があります。そのため「聞いて理解する力」はついても、「自分で考え、言葉にする力」は後回しになります。
将来の大学入試や人生で必要とされる「思考力」「表現力」「積極性」を養う点でも、E-styleの学習は優れています。
子どもたちや保護者の方からは、
「答えよりも考え方を聞かれるようになった」
「答えるときには理由もセットで言うのが当たり前になった」
「学校でも手をあげて意見を言えるようになった」
というお声をよくいただきます。
E-styleの授業では、どんどん手をあげて積極的に参加していただければと思います。
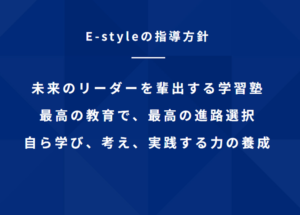
※E-styleのホームページより
3.情報共有と受検生意識
受検が近づくにつれて、「今の勉強で本当に大丈夫だろうか」と不安になることもあるかもしれません。そこでE-styleでは、定期的に保護者会や保護者面談を行い、授業中の様子やご家庭での状況を情報共有しています。
また、これら保護者会や面談、あるいは日々の宿題チェックを通して「ノートの取り方」「丸つけと直しの仕方」など、自立自走に向けた、一人でも効率よく学習する習慣を作ることを低学年のうちから目指します。
早いうちから「本気で合格したい!」という受検生意識を持つことで学習効果はさらに高まります。
4.まとめ
E-styleは、他塾と比べて、
□ 時間的に・体力的に、無理・無駄がない
□ 同じ目標を持つ友だち(ライバル)がたくさんできる
□ 積極的に自分の意見を言葉にできるようになる
□ 目的意識を持って自己管理できるようになる
というのが大きな特長です。
お子さまは、仲間たちと密度の濃い授業を受けて日々成長していきます。
帰宅されたお子さまに、「今日は塾で何を学んだの?」と聞いていただくだけでも、学びの定着に大きく寄与します。ぜひご家庭でも楽しくなるようなお声掛けをお願いいたします。
カテゴリー
新着記事
アーカイブ
- 2026年2月(3)
- 2026年1月(4)
- 2025年12月(4)
- 2025年11月(4)
- 2025年10月(5)
- 2025年9月(5)
- 2025年8月(4)
- 2025年7月(3)
- 2025年6月(4)
- 2025年5月(4)
- 2025年4月(4)
- 2025年3月(4)
- 2025年2月(4)
- 2025年1月(4)
- 2024年12月(4)
- 2024年11月(5)
- 2024年10月(3)
- 2024年9月(4)
- 2024年8月(5)
- 2024年7月(4)
- 2024年6月(3)
- 2024年5月(3)
- 2024年4月(1)
- 2024年3月(2)
- 2024年2月(3)
- 2024年1月(2)
- 2023年12月(4)
- 2023年11月(3)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(5)
- 2023年8月(3)
- 2023年7月(5)
- 2023年6月(3)
- 2023年5月(1)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(3)
- 2023年2月(2)
- 2023年1月(3)
- 2022年12月(4)
- 2022年11月(2)
- 2022年10月(3)
- 2022年9月(3)
- 2022年8月(4)
- 2022年7月(5)
- 2022年6月(2)
- 2022年4月(1)
- 2022年3月(4)
- 2022年2月(2)
- 2022年1月(2)
- 2021年12月(2)
- 2021年11月(3)
- 2021年10月(3)
- 2021年9月(2)
- 2021年8月(2)
- 2021年7月(3)
- 2021年6月(3)
- 2021年5月(2)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(2)
- 2021年2月(4)
- 2021年1月(2)
- 2020年12月(1)
- 2020年11月(1)
- 2020年10月(4)
- 2020年9月(3)
- 2020年8月(1)
- 2020年7月(4)
- 2020年6月(2)
- 2020年5月(1)
- 2020年3月(1)
- 2020年2月(4)
- 2020年1月(1)
- 2019年12月(4)
- 2019年11月(2)
- 2019年10月(2)
- 2019年9月(3)
- 2019年8月(3)
- 2019年7月(3)
- 2019年6月(4)
- 2019年5月(5)
- 2019年4月(3)
- 2019年3月(3)
- 2019年2月(2)
- 2019年1月(2)
- 2018年12月(1)
- 2018年11月(1)
- 2018年10月(2)
- 2018年9月(2)
- 2018年8月(3)
- 2018年7月(4)
- 2018年6月(3)
- 2018年5月(1)
- 2018年4月(2)
- 2018年3月(4)
- 2018年2月(4)
- 2018年1月(3)
- 2017年12月(4)
- 2017年11月(6)
- 2017年10月(3)
- 2017年9月(4)
- 2017年8月(4)
- 2017年7月(4)
- 2017年6月(4)
- 2017年5月(3)
- 2017年4月(4)