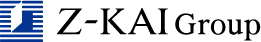簡単に分かったことにしない

執筆者
沖 哲弥
立川国際中等教育学校専門担当
-
所属教室
-
コース
先日上野にある国立科学博物館に行ってきました。
子どものころに行ったときは科学技術を展示する博物館という印象でしたが、今回主に見た地球館の地下2階は、46億年の生物の歴史が展示の中心で、自然史博物館でした。それもそのはず。「科博」と略して言われることもありますが、英語では、National Museum of Nature and Scienceという表記です。サイエンスだけでなく、ネイチャーが含まれているのです。今回はじめて気づきました。
簡単にわかろうとせず、正確に知る。これは難しいです。こちらから関心を向けて知ろうとしないとなかなか本当の姿が見えません。
塾の先生というのは人に説明する仕事なので、ホントかなと詳しく調べたり考えたりする習慣はついているほうですが、それでも「重いコンダーラ」のような思い込みは起きます(古い!)。
それを「絶対に正しいことを教えなくては」「まちがいを言ってはならない」と肩に力を入れるのではなく、生徒たちと一緒に思い込みを発見し修正していくのはなかなかに楽しい作業です。
先日、「太政大臣」はなんて読むんですか、と質問する子がいました。
歴史の本には「だいじょうだいじん」って書いてあるけど、学校の先生は「だじょうだいじん」って言うし、さっきお母さんに聞いても「だじょうだいじん」って言うんです。でも歴史の本には……。
どっちも正しいと初めは答えましたが、よくよく調べてみたら違いました。
国語辞典(小学館)によると、「だいじょうかん【太政官】:律令制で、国政の最高機関。」「だじょうかん【太政官】:明治初期の最高官庁。現在の内閣に当たる。」とあります。つまり、「だいじょうだいじん」が古い読み方ということです。そういうことか! と双方膝を打ったわけです。
侍従の「雑草」という発言に対して、昭和天皇が「雑草という名の草はない。どんな植物にもみな名前があって、それぞれ自分の好きな場所で生きている。人間の一方的な都合でこれを雑草と決めつけてはいけない」とたしなめたというエピソードが私は好きです。
生徒という名前の小学生はいないわけで、一人ひとりに名前があります。それぞれの子が自分から行動を起こし、多くの納得を得られるよう、決めつけを排しながら促したいと思います。

カテゴリー
新着記事
アーカイブ
- 2026年1月(2)
- 2025年12月(4)
- 2025年11月(4)
- 2025年10月(5)
- 2025年9月(5)
- 2025年8月(4)
- 2025年7月(3)
- 2025年6月(4)
- 2025年5月(4)
- 2025年4月(4)
- 2025年3月(4)
- 2025年2月(4)
- 2025年1月(4)
- 2024年12月(4)
- 2024年11月(5)
- 2024年10月(3)
- 2024年9月(4)
- 2024年8月(5)
- 2024年7月(4)
- 2024年6月(3)
- 2024年5月(3)
- 2024年4月(1)
- 2024年3月(2)
- 2024年2月(3)
- 2024年1月(2)
- 2023年12月(4)
- 2023年11月(3)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(5)
- 2023年8月(3)
- 2023年7月(5)
- 2023年6月(3)
- 2023年5月(1)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(3)
- 2023年2月(2)
- 2023年1月(3)
- 2022年12月(4)
- 2022年11月(2)
- 2022年10月(3)
- 2022年9月(3)
- 2022年8月(4)
- 2022年7月(5)
- 2022年6月(2)
- 2022年4月(1)
- 2022年3月(4)
- 2022年2月(2)
- 2022年1月(2)
- 2021年12月(2)
- 2021年11月(3)
- 2021年10月(3)
- 2021年9月(2)
- 2021年8月(2)
- 2021年7月(3)
- 2021年6月(3)
- 2021年5月(2)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(2)
- 2021年2月(4)
- 2021年1月(2)
- 2020年12月(1)
- 2020年11月(1)
- 2020年10月(4)
- 2020年9月(3)
- 2020年8月(1)
- 2020年7月(4)
- 2020年6月(2)
- 2020年5月(1)
- 2020年3月(1)
- 2020年2月(4)
- 2020年1月(1)
- 2019年12月(4)
- 2019年11月(2)
- 2019年10月(2)
- 2019年9月(3)
- 2019年8月(3)
- 2019年7月(3)
- 2019年6月(4)
- 2019年5月(5)
- 2019年4月(3)
- 2019年3月(3)
- 2019年2月(2)
- 2019年1月(2)
- 2018年12月(1)
- 2018年11月(1)
- 2018年10月(2)
- 2018年9月(2)
- 2018年8月(3)
- 2018年7月(4)
- 2018年6月(3)
- 2018年5月(1)
- 2018年4月(2)
- 2018年3月(4)
- 2018年2月(4)
- 2018年1月(3)
- 2017年12月(4)
- 2017年11月(6)
- 2017年10月(3)
- 2017年9月(4)
- 2017年8月(4)
- 2017年7月(4)
- 2017年6月(4)
- 2017年5月(3)
- 2017年4月(4)