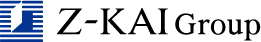「書く力」を身につける第一歩

執筆者
荒海 理恵
公立中高一貫校受検記述指導主任
交換日記を始めませんか?
非常に多くの小中学生が「文を書くこと」を苦手とします。
絵を描くこと、歌をうたうこと、体を動かすことが好きな子は大勢いるのに、文を書くことに苦手意識をもっている子が多いのはなぜでしょうか。
それは、読書感想文に苦しんだ人が多いからかもしれません。あるいは、学校で遠足などに行ったあとに書かされる作文(文集)に苦しんだからでしょうか。
この2つの(学校で書かされる)作文の共通点は、
「自分が感じたことを書く」
ということです。
自分が感じたことを文章にするのは、とてもむずかしいことです。
「読書」とか「遠足」の感想は、結局のところ「おもしろかった」か「おもしろくなかった」の2つです。
それを400字とか800字とか1200字に引きのばすのは、とても大変です。器用な子なら「書くことがなければ嘘を書けばいい」と考えて、その場をしのぎます。
しかし「嘘」をつくとき、なぜかみんな「反省文」を書きます。「今までは~だった。しかしこの本を読んで~と思った。だからこれからは~しよう。」という文ですね。
「これから~する」予定なんてまったくないのに。
そういった「作文を書くときの嘘」が、作文を書くことをよりつらいものにしているのも気付かずに。
文章とは、「自分が感じたことを人にも知ってもらいたい」という気持ちが作り出すものです。(記録文を別にすれば)
自分が感じていないことを書いても、「上手に書けた」という気持ちにはなれないでしょう。目的がないのだから。
逆に言えば、「感じたこと」さえあれば、文章は書けます。SNSに書く文も、仕事で作るプレゼン資料も同じです。誰かと感情を共有したいという気持ちさえあれば、文章はすらすら書けます。
つまり、文章が上手になるためには、「感情を伝える」ことに慣れることだと思います。交換日記をしたことがある子どもは、きまって作文が上手です。交換日記は、感情の伝え合いだからではないでしょうか。
でも、親子での交換日記に子どもが付き合ってくれる時期は、ごく限られています。
小学生のうちに親子でそういう機会が持てれば、文章はかならず上手になるはずです。
E-styleでは小3から「国語・記述」クラスを開講しています。
テーマに対して、考えたことや感じたことを素直に言葉にしてもらいます。正解・不正解はありません。
そして交換日記のように、その場にいる先生がレスポンスをし、言いたいことをどんどん言ってもらいます。クラスメイトもお互いに感じたことを伝え合います。多くのことは否定せず、受け止めてあげることで、さらに発言が増えていきます。そうして「思ったことを言いたい!」「聞いてもらいたい!」という子がクラスの中でたくさん育ちます。相手がお母さんやお父さんでなくても、しっかりと感情を伝えることに慣れていきます。
クラスの中で堂々と「伝える」姿は小3でも頼もしいなと、日々の成長を見て感じます。
カテゴリー
新着記事
アーカイブ
- 2026年1月(3)
- 2025年12月(4)
- 2025年11月(4)
- 2025年10月(5)
- 2025年9月(5)
- 2025年8月(4)
- 2025年7月(3)
- 2025年6月(4)
- 2025年5月(4)
- 2025年4月(4)
- 2025年3月(4)
- 2025年2月(4)
- 2025年1月(4)
- 2024年12月(4)
- 2024年11月(5)
- 2024年10月(3)
- 2024年9月(4)
- 2024年8月(5)
- 2024年7月(4)
- 2024年6月(3)
- 2024年5月(3)
- 2024年4月(1)
- 2024年3月(2)
- 2024年2月(3)
- 2024年1月(2)
- 2023年12月(4)
- 2023年11月(3)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(5)
- 2023年8月(3)
- 2023年7月(5)
- 2023年6月(3)
- 2023年5月(1)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(3)
- 2023年2月(2)
- 2023年1月(3)
- 2022年12月(4)
- 2022年11月(2)
- 2022年10月(3)
- 2022年9月(3)
- 2022年8月(4)
- 2022年7月(5)
- 2022年6月(2)
- 2022年4月(1)
- 2022年3月(4)
- 2022年2月(2)
- 2022年1月(2)
- 2021年12月(2)
- 2021年11月(3)
- 2021年10月(3)
- 2021年9月(2)
- 2021年8月(2)
- 2021年7月(3)
- 2021年6月(3)
- 2021年5月(2)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(2)
- 2021年2月(4)
- 2021年1月(2)
- 2020年12月(1)
- 2020年11月(1)
- 2020年10月(4)
- 2020年9月(3)
- 2020年8月(1)
- 2020年7月(4)
- 2020年6月(2)
- 2020年5月(1)
- 2020年3月(1)
- 2020年2月(4)
- 2020年1月(1)
- 2019年12月(4)
- 2019年11月(2)
- 2019年10月(2)
- 2019年9月(3)
- 2019年8月(3)
- 2019年7月(3)
- 2019年6月(4)
- 2019年5月(5)
- 2019年4月(3)
- 2019年3月(3)
- 2019年2月(2)
- 2019年1月(2)
- 2018年12月(1)
- 2018年11月(1)
- 2018年10月(2)
- 2018年9月(2)
- 2018年8月(3)
- 2018年7月(4)
- 2018年6月(3)
- 2018年5月(1)
- 2018年4月(2)
- 2018年3月(4)
- 2018年2月(4)
- 2018年1月(3)
- 2017年12月(4)
- 2017年11月(6)
- 2017年10月(3)
- 2017年9月(4)
- 2017年8月(4)
- 2017年7月(4)
- 2017年6月(4)
- 2017年5月(3)
- 2017年4月(4)